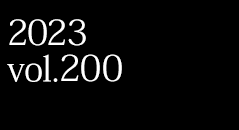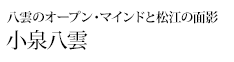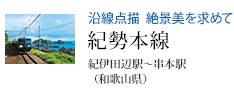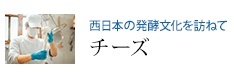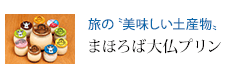1967年10月21日、香川県高松市生まれ。国語辞典編纂者。『三省堂国語辞典』編集委員。辞書を作るため、新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、あらゆる所から現代語の用例を採集し、意味の説明を考える日々を送る。著書に『辞書を編む』(光文社新書)、『知っておくと役立つ 街の変な日本語』(朝日新書)、『日本語をつかまえろ!』(共著・毎日新聞出版)、『つまずきやすい日本語』(NHK出版)、『ことばハンター』(ポプラ社・児童書)、『日本語はこわくない』(PHP研究所)などがある。
私は国語辞典を作る仕事をしています。講演のためによく地方に行きますが、ゆっくり観光する余裕もなく、駅から講演会場、講演会場から駅へと移動して、あたふたと帰途に就くのがいつものことです。「思い出ゼロの旅だなあ」などと自虐的に言っていますが、出張の多いお勤めの人も同じ思いをしているかもしれません。
もっとも、「思い出ゼロ」はさすがに言い過ぎで、移動中に記憶に残ることはあります。
新幹線での移動が多いのですが、車内で過ごす時間はまさに自由の身。各地の食材を使った駅弁を食べるのが最大の楽しみです。
あるいは、駅でおみやげを買うのも忘れてはいけません。漬物やめんたいこなど、ごはんのお供になるものが最近の好みです。
どうも、行った先のことより、駅弁やおみやげにばかり詳しくなっています。これでは、やっぱり「思い出ゼロの旅」ではないかな。
いやいや、そんなことはありません。目的地に着いてからのわずかな移動時間に、私は「ことば観察」と称する散歩をすることがあります。自分たちの作る辞書のために、何か役に立つことばはないか、と探して回るのです。
山口県の徳山駅に降り立った時、構内にあるトラフグの大きな模型が目に入りました。よく見ると、トラフグではなく〈とらふく〉と書いてあります。やっぱり山口県では「フグ」ではなく「フク」なんですね。古い言い方がこの地域に残っているのです。売店にも〈幸ふく弁当〉と、「幸福」「フク」を掛けた駅弁がありました。
駅の掲示板には〈ぶちトク情報!〉と書いてあります。これは何だろう。「ぶち」は、岡山県から山口県にかけて使われる程度表現で、「すごく」の意味で使われます。〈ぶちトク〉は、「すごく得」と「徳山」の「徳」を掛けたのでしょう。
駅周辺には、昭和の雰囲気のあるレトロな商店街があります。洋品店、鮮魚店、食料品店など。どの看板の文字も古風です。洋品店には〈新しいおしやれの発見 ミセスの店〉という看板。「や」の字が大きいのがポイントです。また、鮮魚店の「魚」の下側が「大」になっているなど、学校で習う字形とは違う漢字が多く使われているのも興味をそそられます。
店のおじさん、おばさんと雑談になりました。
「昔はもっとにぎやかやったけど、シャッターを下ろす店が多くなってしもうての」
寂しそうにそう語ります。今では失われつつある懐かしい雰囲気が好きな観光客は、きっと少なくないと思うのですが。
こうした「ことば観察」は、もっとじっくりやりたいところですが、そうもいきません。講演会の主催者の方に車で送っていただいている時も、窓の外に貴重なことばの例を見つけることがあります。でも、「ちょっと停めてください」とは言えません。車はそのまま走り去ります。私は残念に思いながら、「よし、またいつかゆっくり来よう」と決意を固めます。
時には、主催者の方が、車での送り迎えの途中、「せっかくですから」と観光ポイントを通過してくださることもあります。江戸時代をしのばせる町家や、これまで知らなかった寺町、初めて見る美しいお城など。「こんな所があったんだ」と驚きながら、ちょこっとだけ街に挨拶をして、残念ながら、そのまま通過してしまいます。
これは旅のリハーサルだな、と思います。今はこうして通り過ぎるしかない。でも、知らなかった街の魅力を感じることはできました。このままで終わるのはもったいない。改めて計画を立てて、ゆっくり街を歩きに来よう。
その時は、思う存分、土地の風景と名物を楽しもう。そして、街のことばもじゃんじゃん写真に記録しようじゃないか。